学習目標
・ 様々な内科疾患について、その妊娠許容条件を理解する。
・ 妊娠による内科疾患への影響と治療法を理解する。
・ 内科疾患合併妊娠の母体ならびに胎児・新生児に与える影響を理解する。
1.内科疾患と妊娠
妊娠前に内科疾患はそれぞれコントロールが良好であることが望ましく、妊娠許容の条件がある疾患もあり、妊娠する前からカウンセリングや計画的な治療を行うことが重要である。
内科疾患にはそれそれに、母体ならびに胎児・新生児へのリスクが存在する。内科疾患も妊娠により増悪することがあり、治療法を理解しておく必要がある。

2.気管支喘息
妊娠による喘息への影響としては、喘息症状の悪化、不変、改善がそれぞれ1/3ずつ認められる。
妊娠前が軽症例であると妊娠中に増悪することはまれであるが、重症例であると44%が妊娠中に悪化したとの報告がある。
妊娠中のコントロール状態が悪ければ、胎盤に十分な酸素が行き渡らず、母体だけではなく児にとっても早産や低出生体重児、周産期死亡率の増加など様々な弊害が生じる。よって、コントロール状態を良好に維持できれば、喘息が母児に与える影響はほとんどなく、管理が重要である。
経口ステロイド薬は、出生時体重の減少、口唇口蓋裂のリスク増加、子癇前症との関連が指摘されているが、経口ステロイド薬の使用が考慮されるほどの発作の際には、治療しないことの方が母児へのリスクが上回る為、治療をためらわないことも必要である。
他の治療薬は妊娠中の使用は基本的に安全性が示されており、コントロール状態を良好に保つことで胎児・母体を低酸素状態にさらさないことが重要であり、薬剤を継続するメリットがデメリットを大きく上回る。よって妊娠中の喘息治療は、非妊娠時と同様に行うことが重要である。
一方で、患者の多くが薬剤により胎児に悪影響が及ぶ可能性を心配し、約1/3もの人が、「妊娠が判明したら、医療者に相談せずに吸入ステロイドを中断する」との報告もあり、医療者が妊娠前からアドバイスを行うことが重要である。

3.甲状腺疾患
母体の甲状腺ホルモンは胎盤を通して胎児に移行し、全妊娠期間を通じて胎児の発育に中心的な役割を果たしている。特に妊娠初期では絨毛性ゴナドトロピン(hCG)が母体の甲状腺を刺激し、血中甲状腺ホルモン値が上昇するが、この時期に一致して胎児の中枢神経系の重要な器官ができあがる。
バセドウ病や橋本病は女性に多く、発症年齢が生殖年齢とも重なるため、妊娠に合併する疾患として重要である。
甲状腺機能異常は妊娠の成立ならびに周産期の予後に影響を与える為、妊娠前からのカウンセリングと治療計画が重要である。


1)甲状腺機能亢進症
ほとんどはバセドウ病であり、慢性的な経過をとることから、挙児希望のある人において課題となる。
バセドウ病の多くは妊娠中に軽快し、抗甲状腺薬は漸減ないしは中止可能な場合が多いが、未治療やコントロール困難なバセドウ病の場合は、流早産、死産、妊娠高血圧症候群、心不全、甲状腺クリーゼ、低出生体重児、新生児甲状腺機能異常の発症リスクが高くなる。
バセドウ病の管理においては、抗甲状腺薬(チアマゾール、プロピルチオウラシル)の内服が主体となる。
胎芽期でのチアマゾール暴露と形態異常の指摘があるため、妊娠初期(少なくとも妊娠4~7週)はチアマゾールを使用しない方が無難である。プロピルチオウラシルは効果と副作用の点でチアマゾールよりも劣るため、妊娠第2三半期からはチアマゾールに切り替えることが推奨される。
バセドウ病では、甲状腺刺激活性を有する抗TSH受容体抗体が胎盤を通過して胎児に移行するため、約1~2%の新生児に一過性甲状腺機能亢進症が認められるため、注意が必要である。
2)甲状腺機能低下症
母体の未治療の甲状腺機能低下症は、流早産、妊娠高血圧症候群、常位胎盤早期剥離、低出生体重児、分娩後出血などが起こりうる。妊娠初期の母体甲状腺機能低下が児の精神発達に影響することが示唆されているが、妊娠後期までに母体の甲状腺機能を是正していれば児の知能に問題はないことが報告されている。
妊娠中は甲状腺ホルモンの必要量が30~50%増加する。妊娠が判明した時点で既にTSHが上昇し、甲状腺機能低下症のコントロールが不良となっていることが多いため、患者には妊娠反応陽性や月経が遅れているときは、速やかに受診するよう伝えておくことが重要である。
レボチロキシンによる補充を行い、治療の目標は血中TSHの正常化である。
4.全身性エリテマトーデス(SLE)
20歳代の女性に好発するため、妊娠は重要なテーマである。
SLEは妊娠中は落ち着くことも多いが、妊娠・出産を機に増悪することもあり注意が必要である。
SLE患者における妊娠許容条件として、以下の3点が挙げられている。
①維持量のステロイド薬(PSL換算で0.3mg/kg/日以下)で半年以上落ち着いている
②重症の臓器病変(腎機能低下、コントロールが難しい高血圧、肺高血圧など)がない
③患者と家族がSLE患者では妊娠合併症のリスクが上がることや妊娠や出産を機にSLEが増悪する可能性があることを理解し、その上で妊娠を強く希望していること
SLE合併妊娠では、早産や妊娠高血圧症候群などのリスクが高まり、抗SS-A抗体を保有していると、胎児に1%の発症率で房室ブロックの発症がある。
5.糖尿病
胎児の先天奇形や流産の頻度の上昇は、妊娠初期の血糖コントロール不良により生じる。
HbA1cN:7.0%未満(できれば6.0%未満)での妊娠が望ましく、その目標到達後の計画妊娠が勧められる。妊娠前から適切な血糖コントロールが図られていれば、胎児の先天奇形率は上昇しない。


周産期合併症は多岐にわたり、母体合併症としては、糖尿病の悪化、流早産、妊娠高血圧症候群、羊水過多症などがある。
胎児・新生児合併症としては、胎児死亡、巨大児に伴う分娩障害、胎児発育不全、新生児低血糖、新生児呼吸障害等がある。
多くの合併症は、妊娠中の血糖コントロール不良により生じる。
治療は妊婦としての適正な栄養を摂取しつつ、血糖の上昇を防ぐために分食を行う食事療法が基本である。
血糖コントロールの目標は、早朝空腹時血糖 95mg/dl以下、食前血糖値 100mg/dl以下、食後2時間血糖値 120mg/dl以下である。
適切な食事療法を行なっても適切な血糖コントロールが得られない時は、胎児への移行性がほとんどないインスリン療法を行う。
6.特発性血小板減少症(ITP)
ITPは女性に多く、好発年齢が20~40歳であるため、妊娠への対応が重要である。
妊娠中は通常でも血液凝固系が亢進し、血小板消費も亢進するので、特に非寛解のまま妊娠した場合は妊娠中に症状が増悪することがある。妊娠前に診断されていれば、適切な治療により寛解してからの妊娠が望ましい。
合併症としては、頻度は低いが母児それぞれに重篤な出血症状を呈することがある。特に新生児の頭蓋内出血には注意が必要である。
妊娠中の血小板数の目標は、各国のガイドラインによると、3万/μl以上に保つことが勧められている。
治療が必要な際は、妊娠中に比較的安全性の高い、プレドニゾロンあるいは免疫グロブリン大量療法を行う。いずれの治療も無効で、分娩時に出血症状があれば、血小板輸血を検討する。
分娩時の安全といえる血小板数の閾値は明確ではないが、各国のITPあるいは麻酔科ガイドラインによると、経腟分娩であれば5万/μl以上、区域麻酔による帝王切開であれば8万/μl以上が目安となる。
胎児の血小板減少と新生児の頭蓋内出血のリスクへの懸念から、1970年代には全てのITP患者に帝王切開が勧められていたが、1990年代にはその科学的根拠はないとされ、現在は分娩様式は純粋に産科適応で決定している。ただし、胎児の出血リスクから、吸引分娩や鉗子分娩は避けることが望ましい。
今回のまとめ
内科疾患のある患者は、基本的に病状を落ち着かせてからの妊娠が望ましい。
病状により妊娠した際の母体、胎児・新生児に与える影響を知り、妊娠前にリスクの説明と計画的な治療を行うことが大事である。
妊娠中は母児の状態も内科疾患も変化するため、産科医、内科医、新生児医が綿密に連携をとって治療に当たることが重要である。

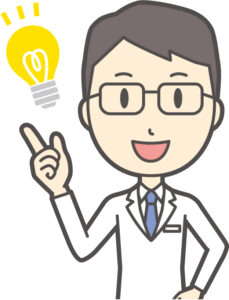

コメント